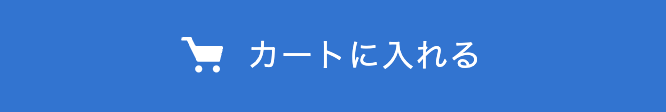土井徳浩『ひとりごと』(QAZZ-002)
¥2,585(税込)
クラリネットという楽器は、音楽史上は比較的新しい楽器である。バロック時代の管楽器と言えば、フルート、オーボエ、リコーダーなどが中心で、クラリネットは存在こそしていたものの、使用されることは極めて稀だった。そんなクラリネットが表舞台に出たのはモーツアルトの功績が大きく、クラリネット五重奏曲(K.581)やクラリネット協奏曲(K.622)はクラリネットの魅力を余すことなく伝える名曲として今もなお演奏され続けている。
クラリネットが他の楽器と決定的に異なる特徴として、それぞれの音域における音色の違いがある。フルートやオーボエ、さらにヴァイオリンなど弦楽器においては、上から下まで割と均一的な音色であるのに対し、クラリネットは高音域、中音域、低音域と、およそ同じ楽器とは思えないほどに色彩豊かである。
モーツアルトの楽曲は、その当時の名手アントン・シュタードラーのために作られたと言われ、とりわけその低音域が好まれていたようだ。
本アルバムのプロデューサーである石田は、中学の吹奏楽部からクラリネットを担当し、高校、大学、社会人とよく演奏していた方だ(現在は押入れに眠っているが)。中学3年の夏、モーツアルトに出会い、そこから石田の音楽人生は急変したとも言える。高校の3年間はモーツアルトのあらゆる楽曲をはじめ、クラリネットの音楽としてはブラームス、ウェーバー、メンデルスゾーン、プーランク、ストラヴィンスキー、シュポアなどをよく聴いていた。
クラリネットはモーツアルト以降のオーケストラにはなくてはならない楽器になっているが、20世紀に登場した新しい音楽、ジャズの世界でも花形となった。デキシースタイルの初期のジャズにおいては、トランペットやトロンボーンなどとの集団即興を繰り広げ、音色的にもクラシックとはまったく異なる色彩を帯びていた。
おそらくクラリネットが最もフィーチャーされた舞台はスイングジャズの時代であろう。ビッグバンドのスタイルで、デューク・エリントン、カウント・ベイシーらと並ぶほどに成功をおさめたのがベニー・グッドマンである。グッドマンはユダヤ系の貧しい家庭に生まれながらも、無料の音楽教室でクラリネットに出会い、腕前を上げる。ジャズのみならず、クラシックにおいても一流の演奏家であった。バルトーク、コープランドなどから作品の提供を受け、さらにレコードにおいてもモーツアルトの見事な演奏が残されている。
しかし、チャーリー・パーカーらによるビバップの革命以降、クラリネットはジャズ界では一線を退き、どちらかと言うとオールドスタイルに属する楽器になったと言える。グッドマンも一時期はビバップに挑戦するものの、最終的には「キング・オブ・スイング」の称号を手離すことなく、晩年まで多くの聴衆を魅了した。
だからと言って、クラリネットはビバップ(モダンジャズ)の影にひっそりと姿を消したわけではなく、バディ・デフランコやトニー・スコットのようなモダンスタイルの演奏家も現れ、その遺伝子は現代にしっかりと受け継がれている。
今回、土井徳浩に「完全なるソロでアルバムを作らないか?」と持ち掛けたところ、寡黙な性格ながら大げさに反応することはなくとも、レコーディングに向けて毎日練習していたようだ。
石田が土井と出会ったのは、中学時代にさかのぼる。中学に入学したばかりの土井が、たった一人で吹奏楽部の見学にやってきた。当時、石田は3年生。土井が最初に手にした楽器はトランペットで、唇が向かなかったのであろう。あまりに音が鳴らないため、顧問の濱田先生から「ナランペット」と言われながら、それでも二年間は頑張った。中3になってすぐのこと、高校3年生の先輩が演奏するベニー・グッドマンの「シング・シング・シング」に衝撃を受け、クラリネットに転向。その後はメキメキと上達し、今や文句なしに日本を代表するジャズクラリネット奏者である。
本アルバムはちょっと欲張ってみた。クラシック、さらにジャズのあらゆるスタイルへの捧げものとして、クラリネット一本で表現してみたい。土井の腕前は良く知っている。だからと言って、モーツアルトやブラームスを一本でやるには無理がある。そこですでにある楽曲として、ストラヴィンスキーの『クラリネットのための3つの小品』を取り上げることにした。
中1で入部した土井は当時から、「好きな音楽はストランヴィンスキーです!」と言い放ち、音楽室で一人、『ペトルーシュカ』を耳コピで黙々と弾いていたのを思い出す。特に習ったこともないピアノで。では、そろそろ楽曲の紹介に入っていきたい。
1.~3. Three Pieces for Solo Clarinet(Ⅰ~Ⅲ)/ Igor Stravinsky
『クラリネットのための3つの小品(Three Pieces for Solo Clarinet)』はストラヴィンスキーのパトロンであった、アマチュアのクラリネット奏者ヴェルナー・ラインハルトに献呈された。3曲からなり、小品だけにそれぞれ演奏時間も1~2分と短いが、極めてバラエティに富む楽曲である。
第一曲は「sempre piano e molt tranquill(常に小さく、極めて静かに)」と指示されており、低い音が出るA管が指定されている。吹奏楽やジャズバンド等では一般的にB♭管が用いられるが、クラシックのオーケストラではA管と二本準備されることが常である。A管はB♭管に比べてしっとりと深い音色を持ち、モーツアルトの五重奏曲、協奏曲、ブラームスの三重奏曲、五重奏曲ではA管が用いられる。
全体を通して低音域で演奏され、調性もなく、ゆったりと長い音符が並べられる。譜面そのものは平易であるが、レコーディングに際して土井はなかなかOKを出さなかった。ちなみに本アルバムは全12曲、一日ですべて録音したのだが、その半分はストラヴィンスキーのこの3曲に費やされた。
第一曲のラスト、突然大きな音が奏でられ、消え入るように小さく終わる。第二曲もそのままA管が指定され、今度は全音域に細かい音符で埋め尽くされ、超絶技巧が要求される。小節線もなく、拍子記号も調性もない。中盤からちょっとだけ旋律的な低音域が続くが、ラストにかけて高音域の猛烈に細かいパッセージが、そして静かに終わる。ショパンの楽曲は、演奏家からは極めてピアニスティックと評されるようだが、それはショパンがピアノという楽器を誰よりも熟知しているからであろう。しかし、この曲はクラリネットという楽器のメカニズムや特性をまったく無視したような難題でありながらも、結局、多くの演奏者に愛されるのも、さすがは「ストラヴィンスキー」だからであろう。
第三曲はB♭管が指定され、これまでの曲と異なり、拍子や調性が細かく目まぐるしく変わる。それだけ自由度が制限されるため、熟達した奏者にとってはかえって演奏しやすいのかもしれない。ラグタイム、つまりジャズの前身とも言えるリズムにインスパイアされ、激しいアクセントとシンコペーションが特徴。
なお、土井自身はこの曲をライブでも演奏したことがあるようで、その時はプーランクのソナタなどもジャズピアニストの伴奏で披露したとのこと。確かに土井のクラリネットはクラシック奏者にも劣らない、引き締まった美しさと気品があり、いつかモーツアルトの五重奏曲なんかを聴いてみたいものだ。
4. Teddy O’Neill / Irish song
石田が個人的に好きな曲で、土井はこの曲を知らなかった。インターネットで楽譜をダウンロードし、収録直前にYouTubeで音源を聴きながらコードを書き込んでいた。20年ほど前、石田がアイルランドを自転車で旅している時に出会った美しい曲。
アイルランドの音楽は主に二種類あり、一つがテンポの速いダンス音楽で、もう一つがエアと呼ばれるバラード。この曲は聴いての通り後者であるが、軽快なダンス音楽とてその歴史は物悲しい。かつてアイルランドがイギリスの支配下にある時代、母国語であるゲールを奪われ、歌ったり踊ったりすることも禁止されていた。しかし人々は踊りたい。窓の外から見られてもばれないよう、上半身を動かさないで踊るスタイルを編み出したとの逸話があり、それがアイルランドダンスの原型となったそうだ。つまり、どっちにしてもアイルランドは物悲しくも美しい。土井はバスクラリネットで演奏している。
5. But not for me / George Gershwin
本アルバムはクラリネット及びジャズの歴史へのオマージュをテーマとしている。ガーシュインの手による大スタンダードだけに、マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーン、チェット・ベイカーをはじめ、ほとんどのジャズミュージシャンが録音している。
しかし、あえて捧げるとすれば、モダンクラリネットの開祖と言ってもよいバディ・デフランコになるだろう。1953年にリリースしたデフランコの代表作『Mr Clarinet』に収録されている。ケニー・ドリューのピアノ、アート・ブレイキーのドラム、ミルトン・ヒントンのベースというゴリゴリのハードバッパーを従えた好演。アップテンポでこれでもかとばかりにバップフレーズを炸裂するのだが、やや単調になりがちなところもある。個人的にデフランコはバラードだと思っているが、ここは土井のアルバムであった。
デフランコのそれよりは気持ちテンポを落としてはいるが、テーマの奏で方はそのまんま。完全なソロで、もちろんマイナスワンを聴きながらなどでは決してない。並の奏者だと迷子になってしまいそうだが、土井は極力アウトせず、コード感をしっかり保ちながらバッパーぶりを発揮している。
6. Anthropology / Charlie Parker
チャーリー・パーカーに捧げようとだけ伝え、石田は録音当日まで知らないでいた。Anthropologyは「人類学」という意味だが、パーカーの曲にはOrnithology(鳥類学)、Crazeology(狂気学?)、Prezology(消毒学?まさか・・)など「~logy」が付くものが目に付く。「~学」という意味で、パーカーが無理やり命名したような無茶なタイトルもあるが、ようは博学なんだろう。YouTubeでその肉声を聞くと、予想以上にインテリくさく、実際、日頃から量子力学の話などもしていたそうだ。
Anthropologyはパーカーの曲の中でも演奏される頻度は高く、スタンダードと言っても差し支えない。ただし、下敷きとなるコード進行はガーシュインの『I Got Rhythm』であり、ジャズマンの間では「リズムチェンジ(循環)」と呼ばれる教科書のような楽曲だ。
土井は冒頭から快調にアドリブで飛ばし、モダンクラリネットの神髄を見せる。ところでクラリネット一本で作られたジャズアルバムとして、海外は把握していないが、国内では北村英治氏が『フル・クラリネット』で吹き込んでいる。その中の『ガーシュイン・メドレー』でI Got Rhythmを挿入しており、一瞬、Anthropologyのフレーズが顔をのぞかせる。同じ楽器で、同じ曲で、まったく異なる世界観を表現しているのが興味深い。
以下、冒頭から3コーラスを写譜してみた。ジャズクラリネット奏者を目指す方は、ぜひ参考にされたい。
7. Stardust / Hoagy Carmichael
言わずと知れた大スタンダードであり、ボーカルではナット・キング・コールが有名。ではインストとなると? パッと思いつくのは、トランペットのクリフォード・ブラウンによるウィズ・ストリングス。しかしそのアルバムは、個人的には大好きなのだが、ジャズアルバムとしてはムーディ過ぎるきらいもある。ここはやはりアーティ・ショウのソロに尽きる。スケールライクでありながら、なんと艶っぽいソロなんだろうか。こんなのモテるに決まってるじゃないか。「一生食えるソロ」を競うなら、『素顔のままで』のフィル・ウッズに比肩すると言っても過言じゃない。およそすべてジャズミュージシャンが目指すべき頂がここにあると言っていい。
後世の人たちは、常に次の頂を目指して登り続けなければならないのでさぞ大変だと思うが、逆に踏みつける素材があるのはありがたい。土井はバースから丁寧に吹き始め、テーマに入ってもリズムは入ってこず、最後まで独り言。リアルな土井は口数が少なく、最低限のコミュニケーションしかしない男であるが、クラリネットを持つと、それはもう饒舌になる。「意外としゃべるんだね」と言いたくなるような、口数(音数)の多いアドリブへと展開するが、まったく煩さを感じさせないのはさすがである。
8. Four / Miles Davis
マイルス・デイヴィスに捧げるなら、何がいいだろうかと考えた。ジャズの歴史を作った張本人だけに、チョイスに困る。1997年、石田はバックパッカーで世界一周をしており、ニューヨークには二週間いながらも、その4~5日はヴィレッジ・ヴァンガードの『SMALLS』というジャズクラブで夜を明かした。10ドル払ってソフトドリンクとスナックが取り放題だったので、宿代だけじゃなく食費まで浮かせたものだ。それでいて、毎晩、良質なライブとジャムセッションが繰り広げられる。
前半はとんでもなく上手い若手が登場するライブで、今ならきっと名のあるミュージシャンになっていることだろう。その後はジャムセッションで入り乱れるのだが、当然、夜中なので眠くなる。寝足りない分は昼間のセントラルパークで補っていたが、半覚半睡で毎晩(または毎夜明け前)に聞こえていたのが、マイルス・デイヴィスのFourだった。石田がジャズに興味を持ち始めた時、マイルス・デイヴィスは天国に旅立っていた。そんな個人的な思い出から、この曲をリクエストした。
土井のソロのバックには常にベースとドラムが聞こえる。だから、ある時は「チーチキチーチキ」と、ある時は「ボンボンボンボン」と口でかぶせながら聞くのが、割と正しい姿勢ではないかと思う。
9. Memories of You / Eubie Blake
クラリネット一本でアルバムを作ろう。ある程度、クラリネット、ジャズを聴いている身として選曲を任されたなら、この曲は真っ先にリストにあがるだろう。石田も当然、そうだった。だから、あえて「外す」ことも最後まで考え、グッドマンに捧げる曲として『Let’s Dance』なども思い浮かべたが、きっと却下されるだろうと思い、最終的にこれになった。
北村英治氏の『フル・クラリネット』でも取り上げられているが、よくよく見ると、そのアルバムの1曲目は本アルバムと同じくクラシック音楽だった。結局、クラリネットとジャズの歴史に捧げると言いながら、念頭にあったのは北村英治氏だったのかもしれない。
個人的な話だが、2000年初頭、遅まきながら新社会人になりたての石田は、仕事が片付かず正月も帰省せずに会社に残っていた。その大晦日、博多のニッコーホテルで北村英治氏の無料カウントダウンライブがあると知り、一人で年越しそばならぬ年越しラーメンを食べてから自転車で向かった。給料も安く、彼女もいない、正月も帰れない。誰に文句を言うこともできず、一人くさっていたあの夜。年が明けた瞬間、アップテンポの『世界は日の出を待っている』が演奏され、しばらく涙が止まらなかった。人生のどん底期の出来事。絶対に成功してやると誓った。あれから20年、まあ、そこそこに満足な人生を送っている。
話を戻そう。Memories of Youはベニー・グッドマンの代表曲であり、映画『ベニー・グッドマン物語』でも効果的に用いられている。最後、グッドマンがカネギーホールでこの曲を演奏したのはフィクションだそうだが、映画の中で恋人の方を向いてお馴染みのイントロから吹き始めた。その恋人の隣にいた男が「君、この後プロポーズされるかもね」と耳打ちしたら、「もう、してるわ」と答えエンドロールに入る。
およそクラリネットでジャズを奏でる身として、プロであれアマチュアであれ、この曲を演奏しない人は皆無である。土井もまたお馴染みのイントロからテーマ、アドリブをワンコーラス、後半のテーマは前半を飛ばしサビからエンディングのカデンツァへ。グッドマン、デフランコ、そして土井が最も敬愛するエディ・ダニエルズへと受け継がれた遺伝子をきちんと踏襲している。
そんなジャズクラリネットの偉大なる先人たちと、そして御年91歳、今もなお現役バリバリで世界に笑顔を届け続ける北村英治氏に、この曲を捧げたい。
10. Not D / 即興
せっかくなので、バスクラで何か一曲。土井の独壇場とも言える完全無伴奏インプロヴィゼーション。確たるテーマがあるわけでもなし、その場で思いつくがままに演奏した。バスクラリネットは普通のクラリネットをさらに一オクターブ下げた楽器であり、吹奏楽ではお馴染みであるが、なかなか一般にお目にかかる機会も少ない。
ジャズの世界で初めてバスクラリネットのソロがフィーチャーされたのは、ジェリー・ロール・モートンの『Someday Sweetheart』であるとネットに書かれてあり、音源がYouTubeにもあがっていたので早速聴いてみた。なるほど、非常に美しい演奏であった。ビッグバンドで時々使用されることはあったそうだが、本格的にひのき舞台にあがったのは、エリック・ドルフィーからである。ドルフィーはアルトサックス、フルート、バスクラリネットを対等に用い、実は石田が初めて買ったジャズのCDはドルフィーの『LAST DATE』である。一曲目にクレジットされている『Epistrophy』の冒頭、バスクラリネットの雄叫びにビックリしてのけぞったのを覚えている。
ドルフィーは存在自体が宇宙人のようで、そのフレーズも独特である。バップとフリーの架け橋と言われることもあるが、よく聞くとフレーズはかなりワンパターン。しかし、そのパターンがドルフィーならではで、聴いているとだんだんと癖になる。
土井の演奏だが、5秒ほど聴いて「ん?ドルフィー?」と思われる可能性を考慮し、「いや、ドルフィーじゃな
いよ、土井だよ」って返答するところまで見越して、後から「Not D」と名付けた。だからと言って、「Not D」をもう一回演奏しろと言われても、それはきっと困難だろう。
11. HAMADA / 即興
タイトル「HAMADA」とは濱田伸明のことである。石田と土井の母校PL学園、かつては高校野球の名門であり、何度も甲子園に出場した。甲子園のPLと言えば、世間をにぎわせたKKコンビをはじめ、中村監督、校歌、胸を握る仕草、アルプス席の一文字など多くの名物を生み出した。吹奏楽を指揮していた濱田伸明先生もその一人である。
楽しそうに棒を振る濱田先生と、吹奏楽部員が作ったオリジナルの応援歌、ユニフォーム、その一体感に憧れ吹奏楽部に入部した生徒も多かった。濱田先生は甲子園名物であると同時に、優れたクラリネット奏者でもあった。世界的チェリストのロストロポーヴィチが大阪で公演をする際、濱田先生は本人指名でしばしばエキストラに出演するほどに。
濱田先生の人柄はどちらかと言うとやんちゃな感じで、なんとなく「やしきたかじん」っぽい雰囲気があった。歌と焼酎を愛し、吹奏楽部のOBOGと酒を酌み交わすことも多かった。
2013年、濱田先生が「そのうちの夢」と昔から言われていた、吹奏楽部OBOGバンドの何度目かの定期演奏会が開かれる9月。濱田先生はしばらくガンをやっており、もしかしたらがあると聞き、石田も土井も駆け付けた。その「もしかしたら」が現実になったのが、演奏会のほんの数日前。その演奏会は追悼となった。
PL学園の吹奏楽部はいわゆる吹奏楽の名門ではなかったが、なぜか有能なプロをたくさん輩出している。そのほとんどがクラリネットであり、ひとえに濱田先生の指導が抜群だったからであろう。素行の良くない石田は何かと怒られることが多かったが、かつては「ナランペット」と名付けられた土井は、クラリネットに転向して早い段階からプロを有望視されているように感じた。
そんな濱田先生に捧げたいと思い、「HAMADA」と先にタイトルを伝え、一発で撮った。完全即興を得意とする土井であるが、普段は現代音楽っぽい無調の世界でフリーキーに鳴らしまくるところ、意外と「曲」であった。
濱田先生はPL学園の音楽教諭になってからも、アメリカに留学していた時期がある。その頃、ジャズバンドでサックスを演奏していたそうで、レスター・ヤングみたいなテナーを吹いていた。土井もまたバークリー音楽大学で研さんを積んでおり、アメリカの空気は共有するところなんだろう。
ちょっとファンキーな雰囲気が全体を包んでいるが、時折、とんでもく哀愁漂う一音を出すことがある。わかってもらえるだろうか。
「ええアルバム、作ったやんけ!」
焼酎を飲みながら天国でほほ笑んでいる先生の顔が目に浮かぶ。もう少し生きててほしかったな。
12. みちくさ / 土井徳浩
土井のオリジナルのクラリネットアンサンブル。バスクラリネットを含む四声で、今回は土井が一人で担当している。「あどけない」って表現がピッタリの平易な音が並ぶ。ランドセル抱えた4人の小学生が田舎道を帰宅する様子。けど、ただでは帰らないよね。なんとなく道草くってたら、気が付けば夕飯時になった。そろそろ帰らないとお母さんに怒られる。どっからともなく豆腐屋の音が聞こえる。学校のチャイムが鳴っている。いそげいそげ。まてまて。昭和の原風景。
「お前の母ちゃん、でべそ!」ってフレーズは今も通じるのだろうか。母ちゃんをdisられるのは、割とダメージがある。「お前の母ちゃんの方が、でべそ!」って言い返す。まるで小学生だが、小学生だから仕方がない。40代になった今もなお心は小学生。ただいま。
最後に土井徳浩について、だいたいはすでに紹介しているからちょっとだけ補足。二枚のリーダーアルバム『Amalthea』『Mr. Professor’s Sanctum』は進化したモダンクラリネットとすこぶる評判もよく、唯一無二の世界観。それ以外、サイドでの録音は多数。
クラリネット一本でアルバムを作る。かなり野心的で、演奏者の技量がモロだしになる危ない企画であったが、かなりいい作品になったのではないだろうか。手の込んだアレンジをすることもなく、そのまんまの素直な土井の「ひとりごと」が聴けると思う。曲もクラシックから、スタンダード、オリジナル、即興とバラエティーに富む。ミディアムテンポの曲があってもよかったかと反省点はあるが、まあ、いいか。ジャズのマニアだけでなく、吹奏楽の諸君にも聴いてほしいな。ありがとうございました。
(石田久二)
土井徳浩/clarinet,bass clarinet
1.Three Pieces for Solo Clarinet Ⅰ(Igor Stravinsky)
2.Three Pieces for Solo Clarinet Ⅱ(Igor Stravinsky)
3.Three Pieces for Solo Clarinet Ⅲ(Igor Stravinsky)
4.Teddy O’Neill(Irish Song)
5.But not for me(George Gershwin)
6.Anthropology(Charlie Parker)
7.Stardust(Hoagy Carmichael)
8.Four(Milse Davis)
9.Memories of You(Eubie Blake)
10.Not D(即興)
11.HAMADA(即興)
12.みちくさ(土井徳浩)
レーベル:QAZZ
企画:石田久二
制作:株式会社フロムミュージック
発売元:まるいひと株式会社